
この記事は、副業をしているサラリーマンや会社員、個人事業主の方に向けて経験豊富な税理士の北村嘉章税理士(北村税理士事務所)が詳しく解説しています。
「副業 税務調査」で検索する方が抱える不安や疑問に対し、税務調査が本当に来るのか、どんな場合に対象になるのか、どのような対策が必要かをわかりやすく解説します。
税務調査の仕組みやリスク、実際の体験談、安心して副業を続けるためのポイントまで、最新情報をもとに徹底解説します。
副業の税金や調査に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
副業で税務調査が来る可能性は?検索ニーズとその背景
副業をしている人が「税務調査が来るのでは?」と不安になる背景には、近年の副業解禁や働き方改革による副業人口の増加があります。また、インターネットやSNSの普及で副業の種類も多様化し、税務署の情報収集力も高まっています。
「副業 税務調査」といったキーボードで検索する人は、申告漏れや無申告によるペナルティ、どの程度の収入で調査対象になるのか、会社にバレるリスクなど、具体的な不安や疑問を抱えています。こうした背景から、正しい知識と対策を知りたいというニーズが高まっています。
サラリーマン・会社員でも税務調査は来る?事例と傾向
サラリーマンや会社員でも、副業で一定以上の収入がある場合は税務調査の対象となることがあります。特に、年間20万円を超える副業所得がある場合は確定申告が必要で、申告漏れや無申告が発覚すると調査が入るリスクが高まります。
最近では、ネットオークションや仮想通貨取引、フリマアプリなど多様な副業が増えており、税務署も情報収集を強化しています。
実際に、会社員が副業収入を申告せずに税務調査を受けた事例も報告されており、油断は禁物です。
| 職業 | 副業収入 | 税務調査の有無 |
|---|---|---|
| サラリーマン | 20万円超 | 調査対象 |
| 会社員 | 20万円以下 | 原則対象外 |
副業が税務調査の対象になる理由と仕組み
副業が税務調査の対象になるのは、税務署がさまざまな情報源から副業収入を把握できる仕組みが整っているためです。確定申告の有無や、支払調書、銀行口座の入出金、SNSでの活動など、複数のルートから副業の存在が明らかになるケースが増えています。
また、税務署はAIやデータベースを活用して不審な取引や申告漏れを自動的に抽出する体制を強化しています。副業が税務調査の対象となる理由や仕組みを理解し、適切な申告と対策を行うことが重要です。
副業はなぜ税務署に発覚するのか?バレる仕組みを解説
副業が税務署に発覚する主な理由は、先ほどの通り支払調書や銀行口座の入出金履歴、SNSでの活動などから情報が集まるためです。
たとえば、企業や取引先が発行する支払調書は税務署にも提出されるため、申告していない副業収入があるとすぐにバレてしまいます。その他、銀行口座の大きな入金や頻繁な取引もチェック対象となりやすく、ネット上での副業活動もAIによって監視されています。
税務署が無申告を把握する仕組みの中核には、国税総合管理システム「KSK(Kokuzei Sougou Kanri System)」があります。このシステムには、企業から提出される法定調書(支払調書など)や過去の申告データ、金融機関の情報など、あらゆる情報が一元管理されています。
KSKが個人の所得情報を網羅的に分析し、申告されているべき所得があるにもかかわらず申告がない個人を自動的に抽出するため、無申告の状態を隠し通すことは極めて困難なのです。
「少額だから大丈夫」と油断せず、正しい申告を心がけましょう。
税務調査が入る『きっかけ』と主な原因—確定申告・収入・取引情報
税務調査が入るきっかけは、確定申告の内容に不審な点があった場合や、収入と申告額に大きな差がある場合、取引先からの情報提供などが挙げられます。
特に、支払調書と申告内容が一致しない、銀行口座に多額の入金がある、SNSで副業を公表しているなど、複数の情報が一致すると調査対象になりやすいです。
また、過去に申告漏れや無申告があった場合も、重点的にチェックされる傾向があります。
以下、副業で税務調査が入るきっかけになる主な項目です。
- 確定申告内容の不一致
- 収入と申告額の差異
- 取引先からの情報提供
- 過去の申告状況
副業で税務調査が行われる仕組みと種類—個人事業主/サラリーマン別解説
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、副業の場合は主に任意調査が行われます。個人事業主は帳簿や領収書の確認が中心ですが、サラリーマンの場合は副業収入の申告状況や支払調書との整合性がチェックされます。
また、調査は事前通知がある場合と、抜き打ちで行われる場合があります。副業の規模や内容によって調査の深さや範囲が異なるため、日頃から正確な記帳と申告が重要です。
| 対象者 | 主な調査内容 |
|---|---|
| 個人事業主 | 帳簿・領収書・経費 |
| サラリーマン | 副業収入・支払調書 |
SNSや銀行口座から判明する副業収入—情報把握の流れ
税務署はSNSや銀行口座の情報からも副業収入を把握しています。たとえば、SNSで副業の成果や売上を公開している場合、その情報が税務署の目に留まることがあります。
また、銀行口座に副業収入が定期的に振り込まれていると、金融機関からの情報提供やAIによる自動抽出で調査対象となることも。ネット社会では情報が簡単に共有されるため、隠しているつもりでも発覚するリスクが高まっています。
副業の税務調査はいくらから・どんな人が対象?
副業の税務調査は、所得が一定額を超える場合や、申告内容に不審な点がある場合に対象となります。特に、サラリーマンの場合は副業所得が年間20万円を超えると確定申告が必要で、これを怠ると調査リスクが高まります。
個人事業主やフリーランスの場合は、売上や経費の規模にかかわらず、無申告や申告漏れがあると調査対象となることがあります。また、過去に指摘を受けた人や、複数年にわたる申告漏れが疑われる場合も要注意です。
税務調査はどの位の金額・売上・所得で来る?ボーダーラインを解説
副業の税務調査が来るかどうかのボーダーラインは、サラリーマンの場合「副業所得が年間20万円超」が一つの目安です。この金額を超えると確定申告が必要となり、申告しない場合は調査対象となるリスクが高まります。
個人事業主やフリーランスの場合は、売上や所得の規模に関係なく、無申告や不自然な経費計上があると調査対象となります。その他、数百万円規模の副業収入がある場合や、複数年にわたる申告漏れが疑われる場合も、税務署のチェックが厳しくなります。
| 職業 | 調査対象となる主な基準 |
|---|---|
| サラリーマン | 副業所得20万円超 |
| 個人事業主 | 無申告・不自然な経費 |
副業バレた・無申告加算税のリスク—知恵袋&体験談を交えたケース比較
副業がバレて税務調査が入った場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることがあります。実際に「副業の申告を忘れていた」「少額だから大丈夫と思っていた」というケースでも、数年後に税務署から連絡が来て追徴課税を受けた体験談が多く見られます。
知恵袋などのQ&Aサイトでも、「副業がバレた」「どんなペナルティがあるのか」といった相談が多く、無申告のリスクは決して小さくありません。
一番の対策は早めの申告と正しい経理が重要です。
調査の確率や年間の発生状況—サラリーマンと個人事業主の違い
税務調査が実際に行われる確率は、全体の納税者数に対して数%程度とされていますが、個人事業主やフリーランスはサラリーマンよりも調査対象になりやすい傾向があります。
サラリーマンの場合は副業所得が20万円を超えた場合や、申告内容に不審な点がある場合に限定されることが多いですが、個人事業主は売上や経費の規模、業種によっても調査の頻度が変わります。
また、過去に指摘を受けた場合や、複数年にわたる申告漏れが疑われる場合は、調査の確率が高まります。
| 職業 | 調査確率 | 主な調査理由 |
|---|---|---|
| サラリーマン | 低め | 副業所得20万円超・申告漏れ |
| 個人事業主 | 高め | 売上・経費・無申告 |
副業で税務調査が来る前にできる対策と注意点
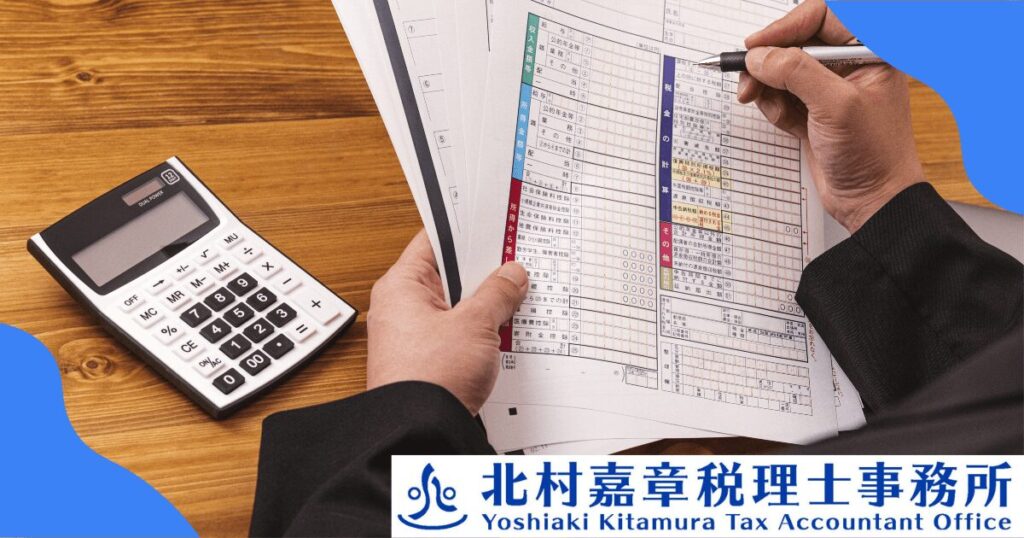
副業で税務調査を受けないためには、日頃から正しい申告と帳簿管理を徹底することが大切です。無申告や申告漏れ、経費の水増しなどは調査のリスクを高めるため、必ず期限内に正確な申告を行いましょう。
また、帳簿や領収書、請求書などの書類はしっかり保存し、税務署からの問い合わせにもすぐに対応できるようにしておくことが重要です。青色申告や税理士への相談もリスク軽減に役立ちます。
申告が必要かどうかのチェックと無申告リスクの回避
まず、自分の副業収入が確定申告の対象かどうかを正確に判断することが最優先です。副業の収入がある場合、申告が必要かどうかの判断基準は「所得(収入-経費)が年間20万円を超えるかどうか」です。
この基準を超える場合、サラリーマンでも確定申告が必要となります。申告しなかった場合は無申告、意図的に隠した場合は脱税とみなされ、重いペナルティが科されることも。
副業の種類や収入形態にかかわらず、収入と経費を正確に把握し、必要に応じて申告することが大切です。不安な場合は税理士への相談がおすすめです。

帳簿作成・請求書・書類保存のポイント—経費計上とトラブル回避
副業で税務調査を回避するためには、日々の帳簿作成と書類保存が不可欠です。売上や経費の記録は、エクセルや会計ソフトを活用して正確に管理しましょう。
請求書や領収書は必ず保管し、経費として計上する際は業務に直接関係するものだけを選びます。書類の保存期間は原則7年とされているため、過去分も整理しておくと安心です。これにより、調査時のトラブルや指摘を未然に防ぐことができます。
青色申告・特別控除・期限内申告によるリスク軽減の方法
副業でも青色申告を選択することで、税務調査リスクの軽減と節税の両立が可能です。副業で青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除が受けられ、節税効果が高まります。
また、期限内に正しく申告することで、無申告加算税や延滞税などのリスクを大幅に減らすことができます。青色申告には複式簿記や帳簿保存などの要件がありますが、会計ソフトを使えば初心者でも対応可能です。
期限を守り、正確な申告を心がけることが、税務調査リスクの最小化につながります。
税理士・税理士法人の活用と無料相談のメリット
副業の税務や申告に不安がある場合は、税理士や税理士法人の活用がおすすめです。専門家に相談することで、正しい申告方法や経費計上のポイント、税務調査への対応策などを具体的にアドバイスしてもらえます。
最近は無料相談を実施している税理士事務所も多く、初めての方でも気軽に相談できます。税理士に依頼することで、調査リスクの低減やトラブル回避にもつながります。
税務調査の流れと副業への対応方法
税務調査は、事前通知から本調査、調査後の対応まで一連の流れがあります。副業の場合も、税務署からの連絡や必要書類の提出、調査官とのやり取りなど、適切な対応が求められます。
事前に流れを把握し、必要な書類やデータを準備しておくことで、慌てずに対応できるようになります。ここでは、税務調査の一般的な流れと副業での注意点を解説します。
税務署からの連絡・通知・電話—事前調査から本調査までのプロセス
税務調査は、まず税務署からの連絡や通知、電話によって始まります。多くの場合、事前に「税務調査を行います」という通知書が郵送され、調査日や調査内容が記載されています。
ただし、抜き打ちで電話がかかってくるケースもあり、特に無申告や申告漏れが疑われる場合は突然の連絡となることもあります。事前調査では、提出済みの確定申告書や支払調書、銀行口座の動きなどがチェックされ、本調査では実際に帳簿や領収書の確認が行われます。
調査官からの質問・必要書類—対応のコツと現金取引の注意
税務調査当日は、調査官から副業の内容や収入、経費について詳細な質問がされます。帳簿や領収書、請求書、銀行口座の明細などの提出を求められることが一般的です。
現金取引が多い場合は、特に入出金の記録や裏付け資料が厳しくチェックされます。質問には正直に答え、曖昧な返答や隠し事は避けましょう。
事前に書類を整理し、分かりやすく説明できるよう準備しておくことがスムーズな対応のコツです。
税務調査当日の具体的な流れ—調査官とのやり取り事例
税務調査当日は、調査官が指定の日時に訪問し、まずは調査の目的や流れについて説明があります。その後、帳簿や領収書、請求書などの書類をもとに、収入や経費の内容を一つずつ確認されます。
調査官は不明点があればその場で質問し、必要に応じて追加資料の提出を求めることも。やり取りは丁寧かつ冷静に行い、分からないことは無理に答えず「後日提出します」と伝えるのも有効です。
調査は数時間から1日程度で終わることが多いですが、内容によっては数日に及ぶ場合もあります。
税務調査後の対応—修正申告・追徴・ペナルティ早見表
税務調査の結果、申告漏れや誤りが見つかった場合は、修正申告を行い、不足分の税金を納付する必要があります。また、無申告や悪質な場合は加算税や延滞税などのペナルティが科されることも。
調査後は、税務署から指摘内容や納付額が通知されるので、速やかに対応しましょう。ペナルティの種類や割合は状況によって異なるため、下記の早見表を参考にしてください。
| 違反内容 | 主なペナルティ |
|---|---|
| 申告漏れ | 過少申告加算税(10%〜15%) |
| 無申告 | 無申告加算税(15%〜20%) |
| 悪質な場合 | 重加算税(35%〜40%) |
税務調査において「悪質」と判断され、重加算税が課される典型的なケースには、以下のようなものが挙げられます。
- 二重帳簿の作成: 税務署に見せるための帳簿と、本当の売上を記録した帳簿を別に作成している。
- 売上の意図的な除外: 特定の取引先からの入金を、意図的に売上から除外している。
- 架空経費の計上: 存在しない外注費や人件費を計上している。
- 資料の破棄・隠匿: 調査官の求めに対し、帳簿や請求書などの資料を意図的に隠したり、破棄したりする。
副業で税務調査を受けた体験談・事例紹介
実際に副業で税務調査を受けた人の体験談や事例は、今後の対策や心構えに役立ちます。サラリーマンや個人事業主、法人化した副業者など、さまざまな立場での調査事例を紹介し、どのような点が指摘されやすいのか、どんな対応が求められるのかを具体的に解説します。
体験談を通じて、税務調査のリアルな流れや注意点を知り、安心して副業を続けるためのヒントを得ましょう。
副業サラリーマンの体験談—申告漏れがバレたケース
副業サラリーマンの中には、「少額だから大丈夫」と思い申告を怠った結果、数年後に税務署から調査の連絡が来たという体験談が多くあります。
たとえば、ネットオークションやフリマアプリでの収入を申告せずにいたところ、支払調書や銀行口座の入金履歴から発覚し、過去数年分の追徴課税を受けたケースもあります。
このような事例では、無申告加算税や延滞税が加算され、思わぬ高額な納税を求められることもあります。「副業だから平気」と油断せず、正しい申告を心がけることが重要です。
個人事業主、副業法人の事例—金額や経費での指摘ポイント
個人事業主や副業で法人化した場合も、税務調査で指摘されやすいポイントがあります。特に、売上の計上漏れや経費の水増し、プライベートと業務の支出が混在している場合は厳しくチェックされます。
たとえば、家事関連費や交際費を過大に経費計上していたことで否認され、修正申告と追徴課税を受けた事例も。法人の場合は、役員報酬や交際費の使い方にも注意が必要です。
正確な帳簿管理と経費の根拠資料の保存が、調査リスクを減らすカギとなります。
副業の税務調査対策まとめ
副業も税務調査の対象です。特に所得が年間20万円を超えた場合の無申告は、支払調書や銀行口座から発覚し、無申告加算税や重加算税など重い追徴課税のリスクがあります。
会社にバレるのを防ぐには、確定申告時に住民税を「普通徴収」にすることが有効です。日々の正確な記帳と証憑保存を徹底し、不安なら税理士に相談することが、安心して副業を続けるための鍵です。

執筆者プロフィール

-
所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年
最新の投稿
お知らせ2025年12月27日北村嘉章税理士事務所が専門メディアに掲載されました
融資2025年11月21日法人4部門の税務調査とは?各部門の違いと対策を税理士が解説
税務2025年11月21日マイクロ法人は税務調査の対象?税理士が特徴や対策を解説
税務2025年11月21日宗教法人の税務調査の実態・頻度・よくある落とし穴を解説



