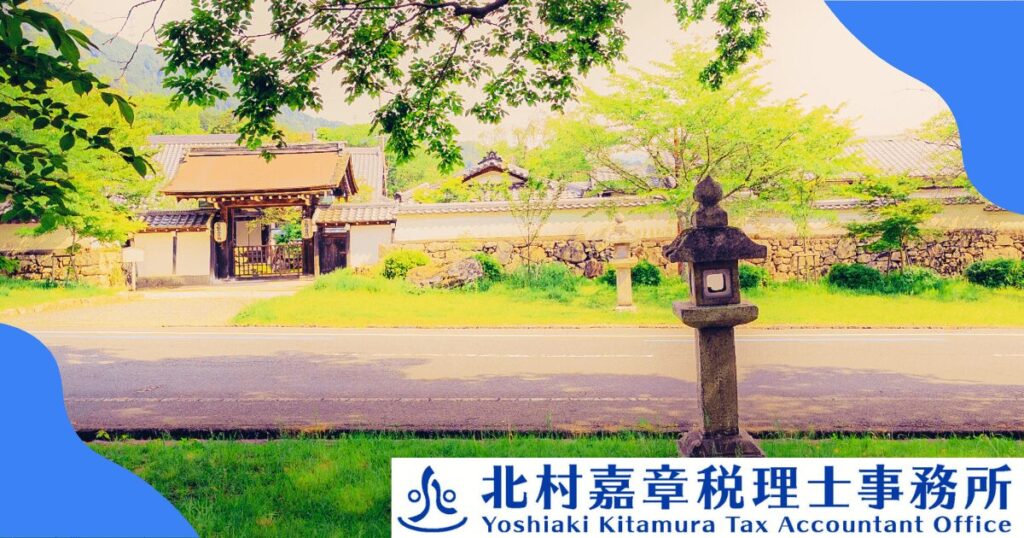
この記事は、寺院・神社・教会などの宗教法人の運営に関わる方や、会計・経理担当者、または顧問税理士の方に向けて宗教法人に対する税務調査の実態や頻度、よくある落とし穴、調査の流れ、調査後のリスクや対応策まで、実務に役立つ情報を経験豊富な税理士の北村嘉章税理士(北村税理士事務所)がわかりやすく解説します。
宗教法人の税務調査に不安を感じている方や、事前に備えたい方はぜひご一読ください。
目次
宗教法人への税務調査とは?基本知識と対象範囲を解説
宗教法人は、宗教活動を主な目的とする法人であり、法人税法上も特別な扱いを受けています。しかし、宗教法人であっても税務調査の対象となることは珍しくありません。
宗教法人への税務調査では、宗教活動による収入(お布施や賽銭など)が正しく計上されているか、収益事業と宗教活動の区分が適切か、帳簿や会計資料が整備されているかなどが重点的に確認されます。
また、宗教法人の役員報酬や不動産収入、物品販売など、課税対象となる取引についても調査の対象となります。宗教法人だからといって税務調査が免除されるわけではなく、適切な会計処理と税務申告が求められます。
なぜ宗教法人も税務調査の対象となるのか
宗教法人は、宗教活動に関する収入(お布施、賽銭など)が非課税となる一方で、収益事業や不動産収入など一部の活動については課税対象となります。
そのため、税務署は宗教法人が非課税と課税の区分を正しく行っているか、収入や支出が適切に処理されているかを確認する必要があります。
また、宗教法人の中には会計処理が不十分なケースや、個人と法人の資金の混同が見られる場合もあり、これが税務調査のきっかけとなることもあります。
税務調査は、税法の適正な運用と公平な課税を確保するために行われているのです。
宗教法人と課税・非課税の違い
宗教法人の収入には、非課税となるものと課税対象となるものがあります。非課税となるのは、布施・賽銭・寄付金・会費など、宗教活動に直接関係する収入です。
一方、駐車場の運営や物品販売、不動産賃貸など、宗教活動以外の収益事業から得られる収入は課税対象となります。この区分を誤ると、税務調査で指摘を受けるリスクが高まります。
また、宗教活動と収益事業の経費の按分や、帳簿の分離管理も重要なポイントです。
| 収入の種類 | 課税・非課税 | 判断基準(理由) |
|---|---|---|
| お布施・賽銭・寄付金 | 原則非課税 | 対価性がないため、宗教活動による収益と見なされる。 |
| お守り・お札 | 原則非課税 | 売価が原価に比べて著しく高額であり、喜捨の性格が強いため。 |
| 線香・ロウソク・絵葉書 | 課税対象 | 一般的な物品販売(収益事業)として判断される可能性が高い。 |
| 墓地管理料 | 非課税 | 宗教活動の一環。(注:墓石の販売斡旋手数料などは課税) |
| 駐車場収入 | 条件により課税 | 参拝者用(無料)は非課税だが、月極やコインパーキングとしての貸し出しは課税対象となる。 |
税務調査で問題視されやすい宗教活動と事業活動の線引き
宗教法人の税務調査で特に問題となりやすいのが、宗教活動と事業活動の線引きです。例えば、法要後の会食や記念品の販売、駐車場の運営などが宗教活動の一環なのか、収益事業なのか判断が難しいケースがあります。
税務署は、実態に即して収入や経費の性質を厳しくチェックします。線引きが曖昧な場合、課税対象と判断されるリスクがあるため、事前に専門家と相談し、明確な基準を設けておくことが重要です。
宗教法人に対する税務調査の実態と頻度
宗教法人に対する税務調査は、一般企業に比べて頻度は低いものの、決して例外ではありません。国税庁の公表データによると、全国の宗教法人のうち、毎年一定数が税務調査の対象となっています。
特に、収益事業を行っている宗教法人や、過去に申告内容に不備があった法人、規模の大きな寺院・神社などは調査対象となりやすい傾向があります。
また、近年はオンライン調査やデータ分析を活用した選定も進んでおり、調査の手法も多様化しています。
宗教法人の税務調査はどれくらいの頻度で実施されているか
宗教法人の税務調査は、全体の法人に比べると頻度は低いものの、毎年数百件から数千件規模で実施されています。
国税庁の統計によれば、令和4年までの5年間で約8,000件以上の宗教法人が調査を受けており、調査を受けた法人のうち高い割合(約7割〜8割など)で指摘を受けてます。
特に、収益事業を行っている宗教法人や、過去に申告漏れがあった法人は調査対象となりやすい傾向があります。また、調査の頻度は地域や法人の規模によっても異なります。
| 調査対象 | 頻度・傾向 |
|---|---|
| 全宗教法人 | 毎年数百~数千件 |
| 収益事業あり | 調査頻度高い |
| 過去に指摘あり | 再調査の可能性あり |
調査に選ばれる寺院・神社の特徴・傾向
税務調査に選ばれやすい寺院・神社にはいくつかの共通点があります。まず、収益事業(駐車場運営や物品販売、不動産賃貸など)を積極的に行っている宗教法人は、課税対象となる取引が多いため調査対象となりやすいです。
また、規模が大きく収入が多い寺院・神社、過去に申告内容に不備があった法人、会計処理が不透明な法人も選定されやすい傾向があります。
さらに、近年はデータ分析やAIを活用した選定も進んでおり、不自然な収支や急激な収入増加がある場合も調査のきっかけとなります。
以下のような特徴がないか確認してみることをおすすめします。
- 収益事業を行っている
- 規模が大きい・収入が多い
- 過去に申告不備がある
- 会計処理が不透明
- 収支に不自然な変動がある
最近の税務署による宗教法人調査の傾向と事例
近年の宗教法人に対する税務調査では、オンライン調査やデータ分析を活用した選定が増えています。また、過去帳や原始記録の確認、現物調査(物品や不動産の現地確認)など、実態把握を重視した調査が行われています。
実際の事例としては、駐車場収入や物品販売収入の申告漏れ、役員報酬の過大計上、寄付金の使途不明などが指摘されています。税務署は、宗教法人の特性を踏まえつつも、課税対象となる取引については厳格に調査を行っています。
税務調査でよく指摘される宗教法人の落とし穴
宗教法人の税務調査では、特有の会計処理や収入の性質から、一般企業とは異なる落とし穴が多く存在します。特に、お布施や寄付金、収益事業の区分、帳簿管理の不備、役員報酬の扱いなどが頻繁に指摘されるポイントです。
これらの落とし穴を事前に把握し、適切な対応を行うことで、調査時のトラブルや追徴課税のリスクを大幅に減らすことができます。以下で、よくある指摘事項について詳しく解説します。
お布施・収益事業・寄付金と課税対象・非課税の判断の落とし穴
お布施や寄付金は原則として非課税ですが、実態によっては課税対象と判断される場合があります。例えば、物品の販売やサービスの対価として受け取った金銭は収益事業とみなされ、課税対象となります。
また、寄付金の名目であっても、特定の対価性が認められる場合は課税されることがあるため、収入の性質を正確に区分することが重要です。
判断に迷う場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

過去帳や帳簿・会計資料の管理不備
宗教法人では、過去帳や帳簿、会計資料の管理が不十分なケースが多く見受けられます。税務調査では、これらの資料が正確かつ適切に保存・管理されているかが厳しくチェックされます。
特に、収入や支出の記録が曖昧だったり、領収書や証憑書類が不足している場合は、経費の否認や申告漏れを指摘されるリスクが高まります。
日頃から帳簿や資料の整理・保存を徹底しましょう。
役員報酬・住職・宮司などへの給与や源泉所得税の問題
住職や宮司、役員への報酬や給与の支払いについても、税務調査でよく指摘されるポイントです。報酬の支払いが適正か、源泉所得税が正しく処理されているか、社会保険の加入状況などが確認されます。
特に、報酬の過大計上や、給与として処理すべきものを経費扱いにしている場合は、追徴課税の対象となることがあります。給与・報酬の支払いは、税法に基づき適切に処理しましょう。
寺院・神社の駐車場・物品販売・不動産収入の課税
寺院や神社が運営する駐車場や物品販売、不動産賃貸などから得られる収入は、原則として課税対象となります。これらの収入を宗教活動の一部として非課税扱いにしていると、税務調査で指摘を受ける可能性が高いです。
また、収益事業にかかる経費の按分や、帳簿の分離管理も重要なポイントとなります。収益事業の収入・経費は、宗教活動と明確に区分して管理しましょう。
| 収入の種類 | 課税・非課税 |
|---|---|
| 駐車場収入 | 課税 |
| 物品販売 | 課税 |
| 不動産賃貸 | 課税 |
税理士や会計担当の知識不足による申告・経理ミス
宗教法人の会計担当者や理士が税務・会計の知識不足により、申告や経理でミスを犯すケースも少なくありません。特に、課税・非課税の区分や、収益事業の経費按分、帳簿の記載方法などで誤りが生じやすいです。
こうしたミスは、税務調査での指摘や追徴課税の原因となるため、定期的な研修や専門家のサポートを受けることが重要です。
税務調査の流れと宗教法人が事前に準備すべきこと

税務調査は、事前通知から実地調査、指摘事項の説明、修正申告や追徴課税の手続きまで、一定の流れで進行します。宗教法人が調査を受ける際は、帳簿や資料の準備、関係者への説明、専門家への相談など、事前の備えが重要です。
ここでは、税務調査の一般的な流れと、宗教法人が準備すべきポイントについて解説します。
税務調査の一般的な進め方と通知(電話・書面・オンライン対応など)
税務調査は、通常、事前に税務署から電話や書面で通知が届きます。近年では、オンラインでの事前説明や資料提出を求められるケースも増えています。
通知後、調査日程や調査内容が説明され、当日は税務署職員が現地に訪問し、帳簿や資料の確認、関係者へのヒアリングなどが行われます。
調査の結果、問題があれば指摘事項が説明され、必要に応じて修正申告や追徴課税の手続きが進められます。
以下、税務調査の一般的な進め方となります。
- 事前通知(電話・書面・オンライン)
- 調査日程・内容の説明
- 現地調査・ヒアリング
- 指摘事項の説明・修正申告
必要となる帳簿・資料・過去帳の準備ポイント
税務調査に備えて、宗教法人が準備すべき主な資料は、会計帳簿、領収書、証憑書類、過去帳、収支内訳書などです。特に、収益事業と宗教活動の収入・経費を明確に区分した帳簿や、寄付金・お布施の記録、役員報酬の支払い記録などが重要です。
資料は、原則として7年間保存する義務があるため、日頃から整理・保管を徹底しましょう。
一般的な質問内容と当日の対応のコツ
税務調査当日には、税務署職員からさまざまな質問がなされます。主な質問内容は、収入や支出の内訳、収益事業の実態、寄付金やお布施の管理方法、役員報酬の決定根拠などです。
質問には正確かつ誠実に答えることが大切ですが、分からないことは無理に答えず、後日資料を提出する旨を伝えるのも有効です。また、調査中は冷静に対応し、記録を残しておくことで、後日のトラブル防止にもつながります。
宗教法人重加算税・追徴課税など調査後に発生するリスク
税務調査の結果、申告漏れや経理ミスが発覚した場合、宗教法人には重加算税や追徴課税などのペナルティが課されることがあります。
特に、意図的な隠蔽や仮装が認められた場合は重加算税が適用され、税負担が大きくなるため注意が必要です。調査後の対応や異議申し立ての流れも把握しておくことで、万が一の際にも冷静に対処できます。
重加算税が課される典型例と法的根拠
重加算税は、意図的な申告漏れや仮装・隠蔽が認められた場合に課される追加的な税金です。例えば、収益事業の収入を意図的に宗教活動収入として隠した場合や、架空経費を計上した場合などが該当します。
重加算税の法的根拠は、国税通則法第68条に定められており、通常の追徴課税に加えて最大で本税の35%が課されることもあります。適正な会計処理と申告が、重加算税リスクの回避につながります。
実際に指摘された課税対象ケース
実際の税務調査では、駐車場収入や物品販売収入の申告漏れ、役員報酬の過大計上、寄付金の使途不明などが指摘されています。また、収益事業の経費を宗教活動の経費と混同して計上していたケースや、帳簿の不備による経費否認も多く見られます。
これらの指摘は、追徴課税や重加算税の対象となるため、日頃から正確な会計処理を心がけることが重要です。
| 指摘内容 | 主なリスク |
|---|---|
| 駐車場収入の申告漏れ | 追徴課税・重加算税 |
| 役員報酬の過大計上 | 経費否認・追徴課税 |
| 寄付金の使途不明 | 課税対象・説明責任 |
調査後の対応・異議申し立ての流れ
税務調査で指摘を受けた場合、まずは修正申告や追徴課税の手続きが求められます。指摘内容に納得できない場合は、税務署に対して異議申し立てや再調査請求を行うことが可能です。
異議申し立ては、調査結果の通知を受けてから60日以内に行う必要があり、必要に応じて税理士や弁護士のサポートを受けると安心です。
冷静に事実関係を整理し、適切な対応を心がけましょう。
宗教法人の税務調査で『おかしい』と感じたときの対応策
税務調査の過程で、調査官の指摘や対応に疑問を感じた場合は、適切な対応を取ることが重要です。税務署への質問や相談、顧問税理士によるセカンドオピニオンの活用、情報公開や不服申立ての手続きなど、複数の選択肢があります。
一方的に指摘を受け入れるのではなく、納得できるまで説明を求める姿勢が大切です。
税務署への質問・相談の方法
税務調査で疑問点が生じた場合は、まず税務署の担当者に直接質問し、説明を求めましょう。質問は口頭だけでなく、書面で行うことで記録が残り、後日のトラブル防止にも役立ちます。
また、国税庁の相談窓口や税務相談センターを利用するのも有効です。納得できるまで丁寧に確認することが、適切な対応につながります。
顧問税理士によるセカンドオピニオンの活用法
税務調査の指摘内容に納得できない場合や、判断に迷う場合は、顧問税理士や第三者の専門家にセカンドオピニオンを求めるのが効果的です。複数の専門家の意見を聞くことで、より客観的かつ適切な対応策を見つけることができます。
また、専門家が税務署との交渉や異議申し立てをサポートしてくれるため、安心して対応できます。
宗教法人が税務調査で押さえるべきポイント
宗教法人の税務調査は、宗教活動と収益事業の区分や帳簿管理、役員報酬の適正な処理など、特有の論点が多く存在します。日頃から正確な会計処理と資料の整理を徹底し、疑問点は専門家に相談することが重要です。
また、調査時には冷静かつ誠実に対応し、納得できない場合は異議申し立てやセカンドオピニオンの活用も検討しましょう。適切な準備と対応が、税務調査のリスクを最小限に抑えるカギとなります。

執筆者プロフィール

-
所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年
最新の投稿
お知らせ2025年12月27日北村嘉章税理士事務所が専門メディアに掲載されました
融資2025年11月21日法人4部門の税務調査とは?各部門の違いと対策を税理士が解説
税務2025年11月21日マイクロ法人は税務調査の対象?税理士が特徴や対策を解説
税務2025年11月21日宗教法人の税務調査の実態・頻度・よくある落とし穴を解説



