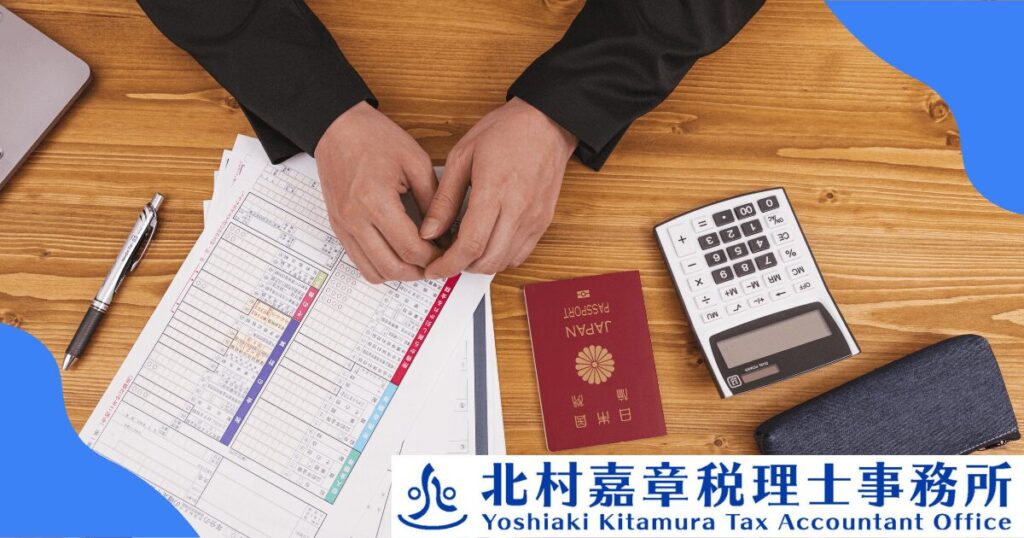
この記事は、個人事業主や中小企業の経営者、経理担当者など、税務調査について不安や疑問を持つ方に向けて経験豊富な税理士の北村嘉章税理士(北村税理士事務所)が詳しく解説しています。
税務調査の基本的な仕組みや流れ、対象となるケース、事前準備や調査時の注意点、調査後の対応まで、税理士の視点からわかりやすく解説します。
税務調査に関する正しい知識を身につけ、安心して対応できるようサポートする内容です。
目次
税務調査とは?基本的な理解を深めよう
税務調査とは、税務署や国税局などの税務当局が、納税者が提出した申告内容が正確かどうかを確認するために行う調査のことです。法人税や所得税、消費税など、さまざまな税目に対して実施され、申告内容に誤りや不正がないかをチェックします。
調査の対象は法人だけでなく、個人事業主やフリーランスも含まれます。
税務調査の定義と目的
税務調査の定義は、納税者が提出した申告書や帳簿、証憑書類などをもとに、税法に基づいて正しく申告・納税が行われているかを税務当局が確認する一連の手続きです。
その主な目的は、大きく以下3点となります。
- 申告内容の正確性を確認し、不正・過少申告・脱税を防止する。
- 納税者の税務意識を高め、適正な納税を促す。
- 公平な課税を実現し、国や自治体の財源を確保する。
税務調査は、納税者が自主的に税金を申告・納付する「申告納税制度」を支える重要な仕組みです。
税務調査とは簡単に言うと?
税務調査を簡単に言うと、「税務署が申告内容に間違いがないかをチェックするための『答え合わせ』」です。
納税者が自分で計算して申告した内容が正しいかどうか、帳簿や領収書などの証拠書類をもとに確認します。調査の結果、問題がなければそのまま終了しますが、誤りや不正が見つかれば修正申告や追徴課税が必要になる場合があります。
税務調査が必要となる理由
税務調査が必要な理由は、納税者が自主的に申告・納税する制度のもと、正確な申告が行われているかを第三者(税務当局)が確認する必要があるためです。
もし税務調査がなければ、不正や過少申告が横行し、税収が減少するだけでなく、正直に納税している人が不公平感を持つことになります。公平な課税を実現し、社会全体の信頼を維持するためにも、税務調査は不可欠な役割を果たしています。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 申告内容の確認 | 正確な納税を担保するため |
| 不正防止 | 脱税や過少申告の抑止 |
| 税収確保 | 国や自治体の財源維持 |
税務調査の種類と流れ
税務調査にはいくつかの種類があり、調査の目的や手続きによって分類されます。主に「任意調査」と「強制調査」に分かれ、任意調査は一般的な税務調査で、納税者の協力を得て行われます。
一方、強制調査は重大な脱税の疑いがある場合などに、裁判所の令状に基づいて行われる厳格な調査です。また、調査の流れは、事前通知から実地調査、調査結果の説明、必要に応じた修正申告や追徴課税といった一連の手続きで構成されています。
調査の種類や流れを理解しておくことで、いざという時に落ち着いて対応できるようになります。
任意調査と強制調査の違い
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。
任意調査は、税務署が納税者に事前通知を行い、協力を得て実施する一般的な調査です。一方、強制調査は、重大な脱税や犯罪の疑いがある場合に、裁判所の令状を得て行われる調査で、納税者の同意がなくても帳簿や資料の押収が可能です。
通常は任意調査がほとんどですが、悪質なケースでは強制調査が行われることもあります。
| 調査の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 任意調査 | 事前通知があり、納税者の協力を前提とする一般的な調査で主に税務署(法人・個人課税部門など)が担当部門となる。 |
| 強制調査(査察) | 裁判所の令状が必要・強制力あり重大な脱税の疑いがある場合に、裁判所の令状に基づき、強制的に行われる厳格な調査で国税局査察部(通称:マルサ)が担当部門となる。 |
税務調査の一般的な流れと手続き
税務調査は、以下の流れで進みます。
- 事前通知: 税務署から電話や書面で調査の通知が届く。
- 日程調整: 調査日程や場所を調整する。
- 実地調査: 調査官が訪問し、帳簿・資料の確認、質疑応答が行われる(通常1日〜数日)。
- 調査結果の説明: 調査終了後、指摘事項や是正すべき点が説明される。
- 事後対応: 必要に応じて修正申告や追徴課税の納付を行う。
税務調査の通知から実施までのスケジュール
税務調査は、通常、調査の1週間から10日前に税務署から電話や書面で通知が届きます。通知後、調査日程や調査場所(事業所や税務署など)を調整し、当日に調査官が訪問します。
調査の期間は1日から数日間に及ぶことが多く、調査内容や規模によって異なります。調査後は、数日から数週間以内に調査結果の説明が行われ、必要に応じて追加対応が求められます。
| ステップ | 期間・内容 |
|---|---|
| 通知 | 調査実施の1週間~10日前に電話や書面で届く。 |
| 日程調整 | 通知後、速やかに行う。 |
| 実地調査 | 11日~数日間。 |
| 結果説明 | 調査後、数日~数週間以内。 |
税務調査の対象と選定基準
税務調査の対象は、法人だけでなく個人事業主やフリーランスも含まれます。調査の選定基準は、申告内容や業種、過去の調査履歴など多岐にわたります。
また、業種や規模によって調査の重点ポイントや調査方法が異なる場合もあります。自分がどのようなケースで調査対象となるのかを知っておくことは、適切な準備やリスク管理に役立ちます。
個人事業主が対象になるケース
個人事業主が税務調査の対象となるケースは、売上や経費の計上に不自然な点がある場合や、申告内容に大きな変動が見られる場合などです。また、業種によっては現金取引が多い場合や、過去に指摘事項があった場合も調査対象となりやすい傾向があります。
経費として認められるかについては、「事業関連性」を主張するために「誰と、どこで、何のために使ったか」を客観的に説明できる証拠を残すことが極めて重要です。例えば、飲食代であれば、領収書の裏に取引先の名称や参加者をメモしておくだけでも、単なる私的な食事ではないことの証明になります。
個人事業主は帳簿や領収書の管理が不十分になりがちなので、日頃から正確な記帳と証憑の保管を心がけましょう。
以下、個人事業主が税務調査の対象となるケースの一例です。
- 売上・経費の計上に不自然な点がある
- 申告内容に大きな変動がある
- 現金取引が多い業種
- 過去に指摘事項がある
その他、自宅兼事務所の家賃や光熱費の計上方法として事業で使用している面積や時間など、合理的な基準で按分していることを説明する場合は、「事務所スペースの床面積の割合で家賃を按分する」「1日のうち事業でPCを使用した時間の割合で電気代を按分する」といった、より具体的な計算例を示すことをおすすめします。
法人における税務調査の特性
法人の場合、税務調査は規模や業種、取引内容に応じて重点的に行われることがあります。特に売上規模が大きい企業や、複雑な取引を行っている法人は調査対象となりやすい傾向があります。
その他には、グループ会社間の取引や海外取引など、税務リスクが高い分野も重点的に調査されます。
法人は内部統制や経理体制の整備が求められるため、日常的な管理体制の強化が重要です。
| 法人の特徴 | 調査のポイント |
|---|---|
| 売上規模が大きい | 売上・仕入の計上、利益操作 |
| 複雑な取引 | グループ間取引、海外取引 |
調査対象の選定基準と近年の傾向
税務調査の対象は、税務署が独自の基準で選定していまがAIやビッグデータを活用したリスク分析に基づいて選定しています。
主な基準としては、申告内容の不自然な点や、過去の調査履歴、業種ごとのリスク、第三者からの情報提供などが挙げられます。
また、無作為抽出による調査も行われており、必ずしも不正が疑われている場合だけが対象になるわけではありません。近年は、電子申告やキャッシュレス決済の普及により、データの突合や不自然な取引の抽出が容易になっています。
選定基準を知ることで、日頃から適正な申告を心がける意識が高まります。
税務調査に向けた事前準備
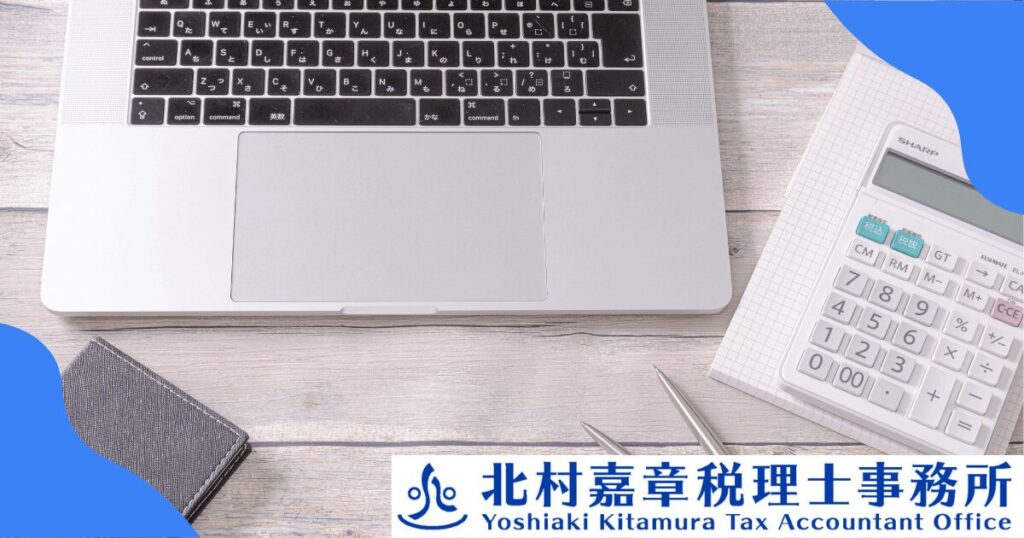
税務調査に備えるためには、日頃から帳簿や証憑書類の整理・保管を徹底することが大切です。また、調査通知が届いた際には、必要書類の準備や過去の申告内容の確認、調査当日の対応方法などを事前に整理しておくと安心です。
税理士などの専門家に相談することで、よりスムーズな対応が可能となります。
必要書類と資料の整理
税務調査に備えて最も重要なのは、必要書類や資料をきちんと整理しておくことです。主な書類としては、帳簿(仕訳帳・総勘定元帳)、領収書、請求書、契約書、預金通帳、給与台帳などが挙げられます。
これらの書類は、調査官から求められた際にすぐに提示できるよう、日付順や取引先ごとにファイリングしておくと良いでしょう。また、電子データで管理している場合は、プリントアウトやデータのバックアップも忘れずに行いましょう。
以下、税務調査に備えて整理をしておきたい内容の項目になります。
- 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳)
- 領収書・請求書
- 契約書
- 預金通帳
- 給与台帳
円滑な対応のための準備事項
税務調査を円滑に進めるためには、事前に調査当日の流れや対応方法を確認しておくことが大切です。調査官が来訪する際には、専用の応接スペースを用意し、必要な書類をすぐに取り出せるようにしておきましょう。
また、調査当日は経理担当者や税理士が立ち会い、質問には正確かつ冷静に答えることが求められます。不明点があればその場で無理に答えず、後日回答する旨を伝えるのも一つの方法です。
税務調査の実施時の注意点
税務調査が実施される際には、調査官とのやり取りや書類の提示方法など、いくつかの注意点があります。調査官の質問には誠実に対応し、事実に基づいた説明を心がけましょう。
また、調査中に不用意な発言や書類の紛失がないよう、慎重な対応が求められます。調査の進行を妨げることなく、冷静かつ協力的な姿勢を持つことが大切です。
対応時の心構えと調査官への対応
税務調査に臨む際は、過度に緊張せず、誠実かつ冷静な対応を心がけましょう。調査官は敵ではなく、あくまで税法に基づいて業務を遂行している立場です。
不明点や疑問があれば、正直に「分かりません」と伝え、後日回答することも可能です。対応は、感情的にならず、事実に基づいた説明を行うことで、調査官との信頼関係を築くことができます。
調査官からの質問にどう答える?
調査官からの質問には、事実に基づいて簡潔かつ正確に答えることが大切です。分からないことや記憶が曖昧な場合は、無理に答えず「確認して後日回答します」と伝えましょう。
推測や憶測で答えることは必ず避け、必ず証拠となる書類やデータをもとに説明すること税務調査官への信頼にもつながります。不安な場合は、税理士に同席してもらうと安心です。
調査中に気をつけるべき誤り
税務調査中にありがちな誤りとして、書類の紛失や誤った説明、不要な情報の提供などが挙げられます。また、調査官の指摘に対して感情的に反論したり、事実と異なる説明をしてしまうこともトラブルの原因となります。
調査中は、必要な書類だけを提示し、質問には簡潔に答えることを意識しましょう。不安な場合は、税理士に相談することをおすすめします。

税務調査後の流れと結果の扱い
税務調査が終了した後は、調査結果の説明や必要に応じた修正申告、追徴課税などの手続きが行われます。調査結果によっては、今後の税務管理体制の見直しや、再発防止策の検討も必要です。
調査後の対応を適切に行うことで、将来的なリスクを最小限に抑えることができます。
調査結果の受け取り方法
税務調査が終了すると、調査官から調査結果の説明があります。この際、指摘事項や是正すべき点、追加で納付すべき税額などが口頭や書面で伝えられます。
調査結果は「指摘事項通知書」や「更正通知書」などの正式な書類で受け取ることが一般的です。内容をしっかり確認し、不明点があればその場で質問しましょう。
調査結果に納得できない場合は、異議申し立てや再調査の請求も可能です。
必要に応じた修正申告の方法
調査結果で申告内容に誤りがあった場合は、修正申告を行う必要があります。修正申告は、税務署に「修正申告書」を提出し、不足分の税金や加算税、延滞税を納付する手続きです。
修正申告は自主的に行うことで、加算税が軽減される場合もあります。手続きが不安な場合は、税理士に相談しながら進めると安心です。
期限内に対応することで、余計なペナルティを避けることができます。
調査結果がもたらす影響とリスク
税務調査の結果、追徴課税や加算税が発生する場合、資金繰りへの影響や信用低下のリスクがあります。重大な不正が認定された場合は、刑事告発や社会的信用の失墜につながることもあります。
一方で、調査を通じて税務管理体制の見直しや、今後のリスク対策を強化するきっかけにもなります。調査後は、指摘事項をしっかりと改善し、再発防止に努めることが重要です。
| 影響 | リスク |
|---|---|
| 追徴課税・加算税 | 資金繰りへの影響 |
| 信用低下 | 社会的信用の失墜 |
| 税務管理体制の見直し | 再発防止の必要性 |
税務調査における専門家への相談・依頼の重要性
税務調査に対応する際は、税理士法人などの専門家に相談・依頼することが非常に重要です。専門家のサポートを受けることで、調査官とのやり取りや書類の準備、調査後の対応までスムーズに進めることができます。
また、トラブルが発生した場合も、適切なアドバイスや交渉を行ってもらえるため、安心して調査に臨むことができます。
税理士法人との連携のポイント
税理士法人と連携する際は、事前に調査の内容やスケジュール、必要書類などを共有し、役割分担を明確にしておくことが大切です。
また、調査当日は税理士が同席することで、専門的な質問にも迅速に対応できます。
日頃から税理士と密にコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておくことが、スムーズな調査対応につながります。
トラブル時の対処法とその対応策
税務調査中や調査後にトラブルが発生した場合は、まず税理士に相談しましょう。調査結果に納得できない場合は、異議申し立てや再調査の請求が可能です。
調査官とのやり取りで行き違いがあった場合も、冷静に事実関係を整理し、書面でのやり取りを心がけると良いでしょう。必要に応じて、弁護士など他の専門家のサポートを受けることも検討してください。
税務調査の頻度とその背景
税務調査の頻度は、業種や規模、過去の申告状況などによって異なります。また、近年はAIやデータ分析技術の進展により、調査対象の選定がより精緻化されています。
税務調査の背景には、税収確保や公平な課税の実現、社会的信頼の維持といった目的があります。調査の傾向や今後の動向を把握し、日頃から適正な申告・納税を心がけることが大切です。
最近の税務調査の傾向
近年の税務調査は、AIやビッグデータを活用したリスク分析が進み、効率的かつ的確に調査対象が選定される傾向にあります。特に、電子申告の普及やキャッシュレス決済の拡大により、データの突合や不自然な取引の抽出が容易になっています。
コロナ禍以降は非対面での調査や書面調査も増加しており、従来の実地調査だけでなく多様な手法が用いられています。このような背景から、日頃からデータ管理や帳簿の整備を徹底することがますます重要となっています。
業種別の税務調査の実施状況
税務調査の実施状況は業種によって大きく異なります。現金取引が多い飲食業や小売業、建設業などは調査対象となりやすい傾向があります。
また、医療・福祉、IT関連、輸出入を伴う貿易業なども、特有のリスクや複雑な取引があるため重点的に調査されることがあります。
一方で、定期的な調査が少ない業種でも、申告内容に不自然な点があれば調査対象となるため、どの業種でも適正な申告が求められます。
| 業種 | 調査の特徴 |
|---|---|
| 飲食業・小売業 | 現金取引が多く重点調査 |
| 建設業 | 下請け取引や経費計上の確認 |
| 医療・福祉 | 保険請求や補助金の適正性 |
| IT・貿易業 | 複雑な取引や海外送金の確認 |
「税務調査とは」のまとめ
税務調査とは、税務署が申告内容の正確性を確認する手続きです 。法人・個人事業主が対象で、公平な課税が目的です 。
多くは事前通知がある任意調査で、帳簿や証憑書類を基に調査されます が誤りがあれば修正申告や追徴課税が必要となります 。
日頃からの正しい記帳と、調査が来た際の税理士との連携が、リスクを減らす最も重要な対策です 。不安な部分も多いと思いますので、そうした方は税務調査の専門家である税理士へ一度相談してみる事をおすすめします。

執筆者プロフィール

-
所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年
最新の投稿
お知らせ2025年12月27日北村嘉章税理士事務所が専門メディアに掲載されました
融資2025年11月21日法人4部門の税務調査とは?各部門の違いと対策を税理士が解説
税務2025年11月21日マイクロ法人は税務調査の対象?税理士が特徴や対策を解説
税務2025年11月21日宗教法人の税務調査の実態・頻度・よくある落とし穴を解説



