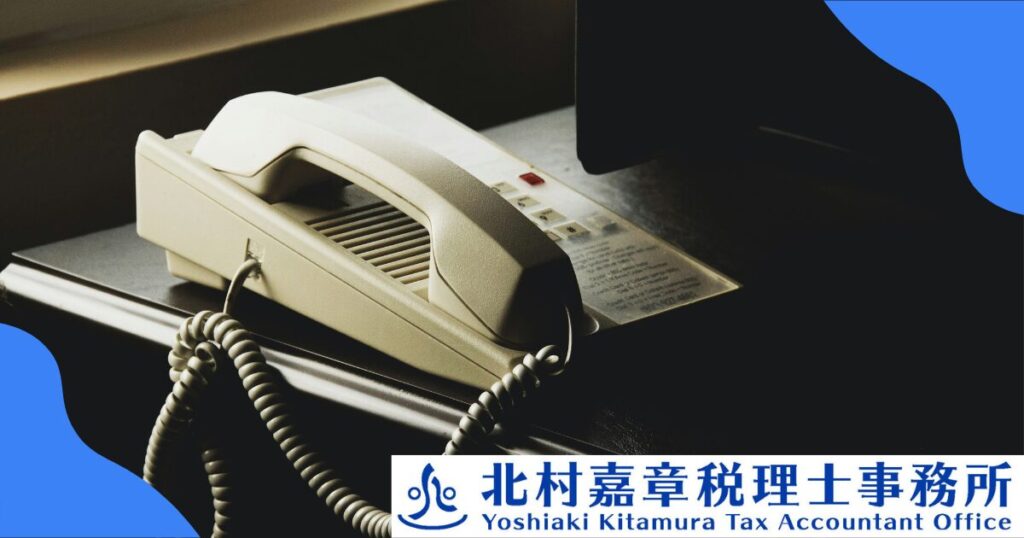
この記事は、税務署から突然電話がかかってきて「税務調査は電話だけで終わるのか?」と不安や疑問を感じている個人事業主や法人経営者、相続税の申告者など、納税者全般に向け経験豊富な税理士の北村嘉章税理士(北村税理士事務所)が詳しく解説しています。
税務調査の電話連絡の実態や、電話のみで済むケース・済まないケース、正しい対応方法や注意点、専門家への相談方法まで、最新の情報をもとにわかりやすく解説します。
突然の電話に慌てず、適切に対応するための知識を身につけましょう。
目次
税務調査で税務署から突然電話が来る理由と基本的な流れ
税務署から突然電話がかかってくると、多くの方が驚きや不安を感じるものです。実際、税務調査の連絡は書面だけでなく、電話で行われることも増えています。
電話連絡の主な理由は、調査の事前通知や日程調整、簡易的な確認事項の伝達などです。また、税務署側も効率的な調査や納税者の負担軽減を目的に、電話での連絡を活用しています。
電話が来た場合は、慌てずに相手の所属や氏名、連絡内容をしっかり確認し、必要に応じてメモを取ることが大切です。
電話のみで調査が完結する場合もあれば、その後に書面や訪問調査へ発展するケースもあるため、流れを理解しておくことが重要です。
電話や書面による調査が増えている背景
近年、この書面調査が増加している背景には、国税当局の効率化戦略があります。
まず、データ分析の進化として納税者の提出した申告データと、金融機関や取引先からの情報(支払調書など)をAIで瞬時に照合することで、小さな不整合点を自動で特定できるようになりました。
次に、リソースの集中として軽微な案件をリモートで解決することで、調査官は限られた人員リソースを、より深刻な脱税が疑われる高リスクな実地調査に集中させることができます。
これらの理由から税務調査を効率化させる動きが出てきています。
税務署や国税局から電話が来るケースと通知の特徴
税務署や国税局から電話が来るケースは、主に税務調査の事前通知や日程調整、追加資料の依頼、申告内容の簡単な確認などです。
電話通知の特徴として、調査官の氏名や所属、連絡先が明確に伝えられる点が挙げられます。
また、電話の内容は必ずしも即時対応を求めるものではなく、後日書面での通知や資料提出を求められることもあります。
一方で、税務署を装った詐欺電話も増えているため、相手の身元や連絡先を必ず確認し、不審な場合は折り返し公式番号に連絡することが重要です。電話通知は納税者の負担軽減や迅速な対応を目的としていますが、内容によっては慎重な対応が求められます。
なぜ電話だけで連絡があるのか?電話調査の理由と実情
税務調査で電話のみの連絡が増えている背景には、調査の効率化や納税者の負担軽減、コロナ禍による対面接触の回避などがあります。
また、申告内容に大きな問題がない場合や、簡単な確認事項のみの場合は、電話での調査が選ばれる傾向にあります。特に、相続税や個人事業主の簡易な申告内容確認、追加資料の依頼などは電話で済むことが多いです。
ただし、電話のみで調査が完結するかどうかは、調査内容や納税者の状況によって異なります。電話調査の実情としては、納税者の協力が得られやすく、迅速な対応が可能な一方、誤解やトラブルを防ぐためにも会話内容の記録が重要です。
『簡易な接触(電話・書面)』で調査は完結するのか?実地調査との違い
「税務調査は電話だけで終わるのか?」という疑問を持つ方は多いですが、実際にはケースバイケースです。電話のみで完結する場合もあれば、電話の後に書面での資料提出や、最終的に実地調査(訪問調査)に発展することもあります。
電話調査は、主に簡単な確認や追加資料の依頼、事前通知などに使われることが多く、申告内容に大きな問題がなければ電話のみで済むこともあります。
一方、疑問点が解消されない場合や、申告内容に不審な点がある場合は、書面調査や実地調査に移行することが一般的です。
それぞれの調査方法には特徴があり、納税者の状況や調査の目的によって使い分けられています。
| 調査方法 | 主な内容 | 完結するケース |
|---|---|---|
| 電話調査 | 簡易な確認・通知 | 軽微な確認のみ |
| 書面調査 | 資料提出の依頼 | 追加資料で解決 |
| 実地調査 | 現地訪問・帳簿確認 | 重大な疑義がある場合 |
電話のみで済む場合・済まない場合の違い
税務調査が電話のみで完結するかどうかは、調査の目的や申告内容の状況によって大きく異なります。
例えば、申告内容に明らかな誤りや疑問点がなく、追加で簡単な確認や資料提出だけで済む場合は、電話のみで調査が終了することが多いです。
一方で、電話でのやり取りで疑問が解消されなかったり、申告内容に不審な点が見つかった場合は、書面での追加調査や実地調査に発展することがあります。
また、納税者が電話での説明に不安を感じた場合や、調査官がより詳細な確認を必要と判断した場合も、電話だけでは終わらないケースが多いです。
電話調査が完結するかどうかは、調査の内容や納税者の対応次第で変わるため、慎重な対応が求められます。
電話調査が選ばれる業種や事業の特徴
電話調査が選ばれやすい業種や事業にはいくつかの特徴があります。主に個人事業主や小規模法人、相続税の申告者など、比較的取引規模が小さく、申告内容がシンプルなケースが該当します。
また、過去の申告内容に大きな問題がなく、税務署側がリスクが低いと判断した場合も、電話調査が選ばれる傾向にあります。
一方で、現金商売や複雑な取引が多い業種、大規模法人などは、電話調査だけで済むことは少なく、実地調査や書面調査が行われることが一般的です。
以下のように、業種や事業規模、申告内容の複雑さによって、調査方法が選ばれています。
| 業種・事業 | 電話調査の傾向 |
|---|---|
| 個人事業主 | 選ばれやすい |
| 小規模法人 | 選ばれやすい |
| 相続税申告者 | 選ばれやすい |
| 現金商売・大規模法人 | 電話のみは少ない |
調査の流れ:電話→書類提出→訪問に発展するケースを解説
税務調査は、最初は電話での連絡から始まることが多いですが、その後の流れは状況によって異なります。一般的な流れとしては、まず電話で事前通知や簡単な確認が行われ、必要に応じて書類の提出を求められます。
提出された書類で疑問点が解消されれば、調査は電話と書面のみで終了します。
しかし、書類の内容に不備があったり、追加で確認が必要な場合は、実地調査(訪問調査)に発展することもあります。電話調査はあくまで調査の入口であり、納税者の対応や提出資料の内容によって、調査の深度が変わる点に注意が必要です。
税務調査の電話対応で絶対にやってはいけないこと
税務調査の電話対応では、納税者がやってはいけないNG行動がいくつかあります。まず、税務署からの電話を無視したり、適当に受け答えをしてしまうことは絶対に避けましょう。また、調査官の身元や連絡先を確認せずに個人情報や重要な内容を話してしまうのも危険です。
焦ってその場で全て答えようとせず、わからないことは「確認して折り返します」と伝えるのが安全です。
さらに、会話内容をメモせずに対応すると、後でトラブルになる可能性があるため、必ず記録を残しましょう。
以下のポイントを守ることで、トラブルや誤解を防ぐことができます。
- 電話を無視・放置しない
- 調査官の身元確認を怠らない
- 焦って全て答えない
- 会話内容を必ずメモする
税務署からの自動音声や不審な電話への応答方法
最近では、税務署を装った自動音声や不審な電話が増えています。税務署からの正式な連絡は、基本的に調査官の実名と所属が伝えられるため、自動音声や不明な番号からの電話には注意が必要です。
不審な電話がかかってきた場合は、絶対に個人情報や口座番号などを伝えず、相手の名前や連絡先を確認しましょう。必要であれば、税務署の公式番号に折り返して事実確認を行うことが大切です。
また、詐欺の可能性がある場合は、すぐに警察や消費者センターに相談することも検討しましょう。
電話を無視した場合のリスクと対策
税務署からの電話を無視したり、折り返し連絡をしない場合、調査が進展しないだけでなく、税務署側が書面通知や実地調査に切り替える可能性が高まります。また、連絡が取れないことで「協力的でない」と判断され、調査が厳しくなることもあります。
最悪の場合、無予告での訪問調査や、加算税・重加算税のリスクも生じます。電話に出られなかった場合は、必ず折り返し連絡をし、誠実に対応することが重要です。
不安な場合は、税理士や専門家に相談しながら対応しましょう。

税務署・税務調査官との会話で注意したい事項とメモの重要性
税務署や税務調査官との電話での会話では、必ず相手の氏名・所属・連絡先を確認し、会話内容を詳細にメモしておくことが重要です。
また、わからないことや即答できない内容は「確認して折り返します」と伝え、無理に答えないようにしましょう。会話の記録は、後日のトラブル防止や、税理士に相談する際の資料としても役立ちます。
また、調査官の指示や依頼事項は正確にメモし、対応漏れがないように注意しましょう。このような基本的な対応を徹底することで、安心して税務調査に臨むことができます。
相続税の税務調査:電話調査の特徴と選ばれやすい家庭の傾向

相続税の税務調査では、電話による調査が選ばれるケースが増えています。特に、申告内容が比較的シンプルで、申告漏れや無申告のリスクが低いと判断された家庭では、電話での簡易な確認や追加資料の依頼のみで調査が完了することもあります。
一方で、財産の内容が複雑だったり、過去の申告に不審な点がある場合は、電話調査から書面調査や実地調査に発展することも少なくありません。
また、相続人が複数いる場合や、財産の分割が複雑な場合も、電話だけで済まない傾向があります。このように、相続税の税務調査は家庭ごとの状況や申告内容によって調査方法が選ばれます。
税務調査の電話対応—納税者として正しい対応と事前準備
税理士や専門家に依頼するメリットと費用相場
税務調査の電話対応やその後の調査に不安がある場合、税理士や専門家に依頼することで多くのメリットがあります。専門家は税務署とのやり取りや資料の準備、調査時の立ち会いなどをサポートしてくれるため、納税者の負担やリスクを大幅に軽減できます。
また、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることで、調査官とのやり取りもスムーズに進みます。費用相場は、電話相談のみなら1万円~3万円程度、調査立ち会いまで依頼する場合は5万円~20万円程度が一般的です。
状況に応じて、必要なサポートを選ぶと良いでしょう。
| 依頼内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 電話相談のみ | 1万円~3万円 |
| 調査立ち会い | 5万円~20万円 |
必要な資料・記録・書類の準備とチェックリスト
税務調査の電話対応やその後の調査に備えて、必要な資料や書類を事前に準備しておくことが重要です。主な準備物としては、申告書の控え、帳簿や領収書、通帳のコピー、契約書類、相続の場合は遺産分割協議書や財産目録などが挙げられます。
また、過去のやり取りや調査官からの連絡内容も記録しておくと安心です。以下のチェックリストを参考に、抜け漏れがないように準備しましょう。
- 申告書の控え
- 帳簿・領収書
- 通帳のコピー
- 契約書類
- 相続関係書類(遺産分割協議書・財産目録など)
- 過去のやり取り・連絡内容の記録
電話・書面調査(デスクレビュー)のまとめ
税務調査は、効率化のため電話や書面のみで行われる書面調査が増加しています。これは実地調査の前段階であり、対応を誤ると現場調査に移行するリスクがあります。
最初の電話通知直後に税理士へ相談するのが最重要対策です。税理士は資料の精査や調査官との交渉を代行し、実地調査への移行を防ぐ「ゲートキーパー」の役割を果たします。求められた資料以外は出さず、迅速かつ正確に、法的根拠に基づき対応することが成功の鍵です。

執筆者プロフィール

-
所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年
最新の投稿
お知らせ2025年12月27日北村嘉章税理士事務所が専門メディアに掲載されました
融資2025年11月21日法人4部門の税務調査とは?各部門の違いと対策を税理士が解説
税務2025年11月21日マイクロ法人は税務調査の対象?税理士が特徴や対策を解説
税務2025年11月21日宗教法人の税務調査の実態・頻度・よくある落とし穴を解説



